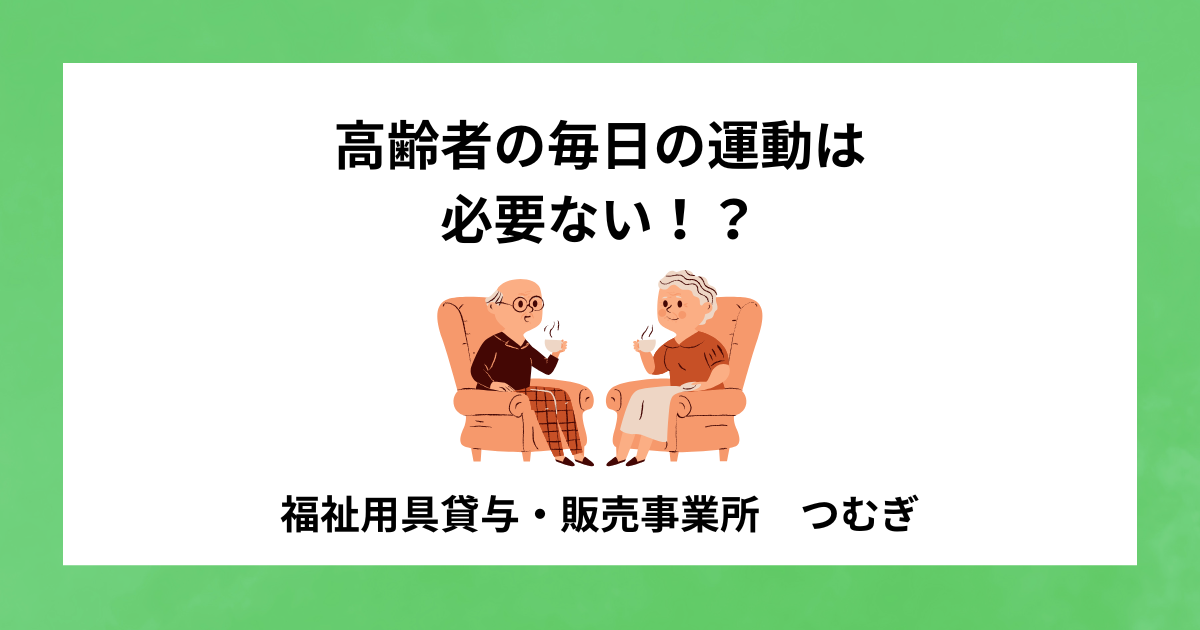
こんにちは。株式会社BooSTの畠山です。
今回は「高齢者の毎日の運動は必要ない!?」についてお話しをさせていただきます。
参考文献
今回は「イチからわかる!サルコペニア Q&A」を参考にさせていただきました。
筆者は筑波大学 山田 実氏です。
リンクを記載しますので、詳細を知りたい方はご参照ください。
https://www2.human.tsukuba.ac.jp/faculty_j/yamada-minoru
はじめに
resistance exerciseは筋肉に負荷をかけて、繰り返し行う運動を指します。

骨格筋の蛋白質の同化が促進されるので、筋力や骨格筋量のUPには非常に効果的な運動です。
(写真)
職業が運送業の方と、事務の方では、骨格筋量に差があることは一目瞭然だと思います。
しかし、resistance exerciseの効果は永続的に持続するわけではありません。
高校を卒業して、運動に取り組む機会が減少すると、骨格筋量の減少だけでなく、肥満に頭を抱える方も一定数いると思います。
骨格筋量の減少は有害健康転帰(adverse health outcomes)の発生に繋がる原因となります。
有害健康転帰とは、転倒、入院、要介護への移行、死亡など、健康に有害となるイベンが発生することを指します。
そのため、resistance exerciseによる効果を維持し、健康寿命の延伸に繋げるためには、運動の継続または再開が必要となります。
本日は、resistance exerciseの効果の持続性について解説をしたいと思います。
効果の持続性
resistance exerciseで獲得した筋力や骨格筋量は、運動実施期間の約2倍の期間をかけて元の状態へ戻るとされています。
resistance exerciseを12週間かけて実施して、その後を追跡をした研究があります。
この研究によると、この期間でUPした筋力と骨格筋量は、中止と共に減弱が始まることが示唆されています。
運動休止12週間後に、効果は半減します。
運動休止24週間後には、効果がほぼ消失します。
そのため、運動期間と同期間の休止は許容範囲と言えそうです。
運動を中止しても、再開したら問題ありません。
しかし、高齢者の場合、運動の実施、休止、再開といった管理を行うことは困難です。
基本的には運動を継続・習慣化させていくことが大切だとされています。
理学療法士の役割
日常生活動作(Activities of Daily Living:ADL)を維持し、有害健康転帰の発生を予防するためには、運動の総実施時間の確保が重要です。
この視座で考えると、高齢者の場合は、高負荷・低頻度のトレーニングは必要ではありません。
低負荷・高頻度でのトレーニングを継続する方が優先度としては高いと言えます。
現代は、時間に余裕がある方が少なく、日常生活の中で運動ができる仕組みづくりが重要です。
運動指導を行う際は、利用者の環境や個性も鑑みて、運動の継続に重点を置く方が建設的な考えです。
併せて読みたい記事
↓運動の総実施時間が〇〇以上でサルコペニアを予防できる!?↓
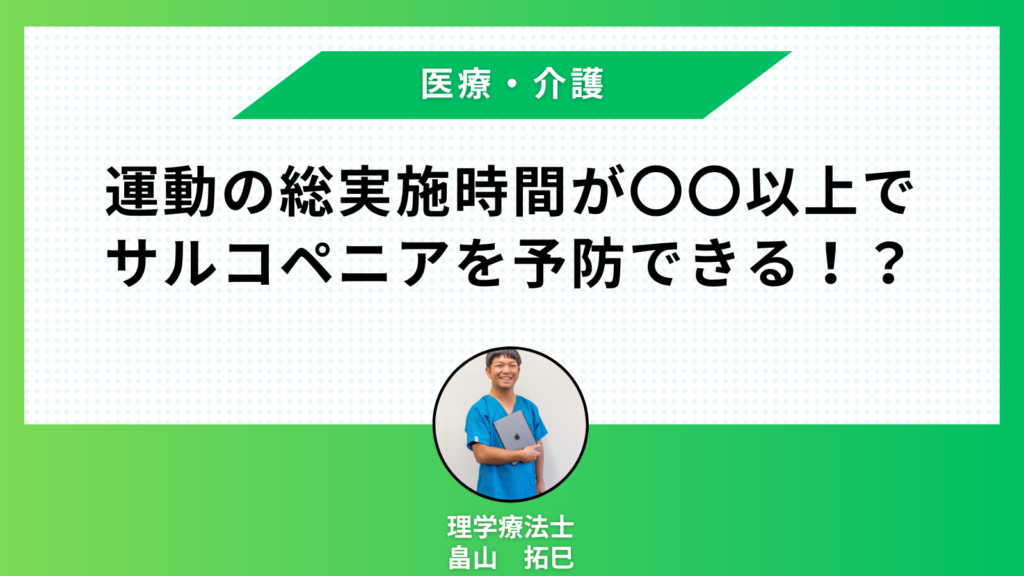
併せて読みたい記事
↓高齢者の“筋トレ”は低負荷・高頻度の運動で効果が出る!↓
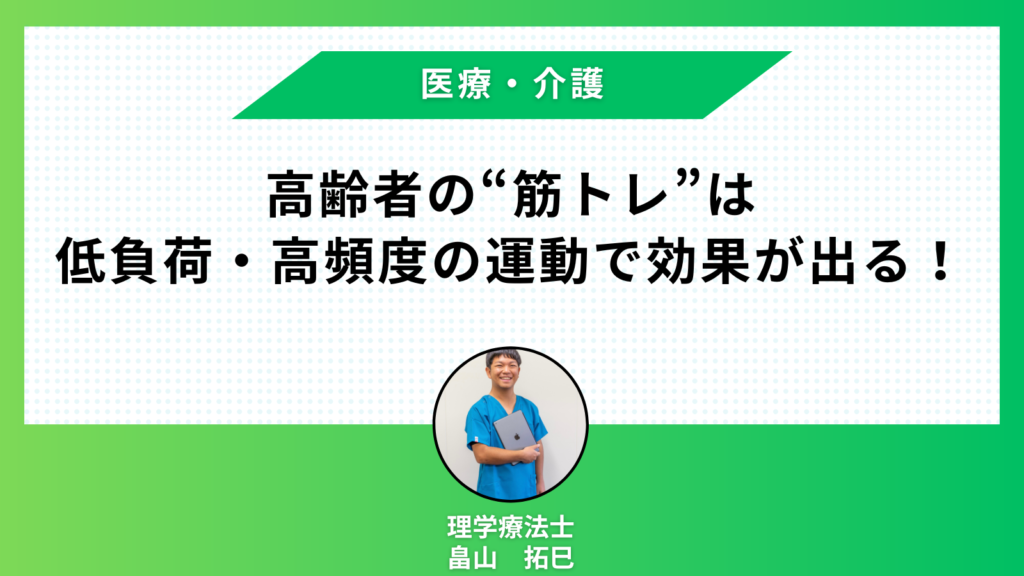
おわりに
今回はresistance exerciseの効果の持続性について解説しました。
resistance exerciseの効果は永続的ではありません。
筋力や骨格筋量は、運動実施期間の約2倍の期間をかけて元の状態へ戻るとされています。
この特性を把握した上で、運動を継続するための仕組みづくりが重要だと言えます。
BooSTは合同会社MYSと連携して訪問リハビリテーションを提供しています。
五島市にお住まいの方はこちらのホームページもご覧ください。