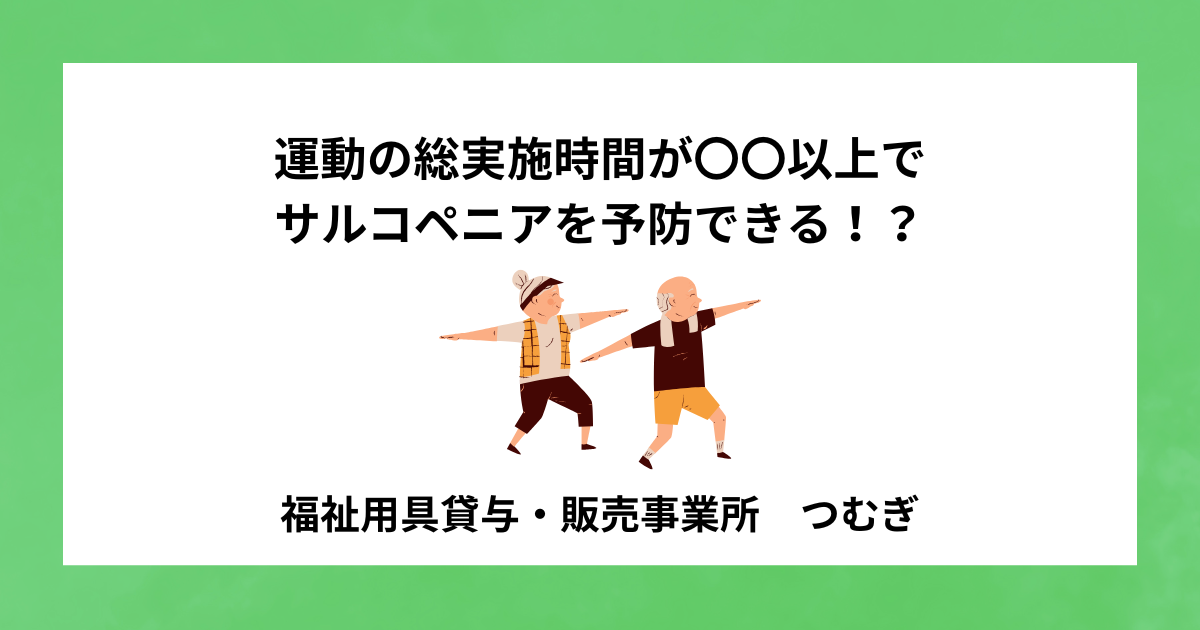
こんにちは。株式会社BooSTの畠山です。
今回は「運動の総実施時間が〇〇以上でサルコペニアを予防できる!?」についてお話しを致します。
参考文献
今回は「イチからわかる!サルコペニア Q&A」を参考にさせていただきました。
筆者は筑波大学 山田 実氏です。
リンクを記載しますので、詳細を知りたい方はご参照ください。
https://www2.human.tsukuba.ac.jp/faculty_j/yamada-minoru
はじめに
私は、地方自治体や地域の高齢者の方々を対象に運動の指導を行う機会をいただくことがあります。
併せて読みたい記事
↓長与町の健康推進ボランティア団体の方々に講義を行いました!↓

健康に関心や興味がある方から、運動の期間・時間・頻度・負荷量の設定についての質問を受けます。
運動の期間・時間・頻度・負荷量の組み合わせは無限にあります。
また、現病歴、既往歴、職業歴、生活歴などの個人因子を考慮した場合、この疑問に関しての最適解を導くことは不可能だと言えます。
そのため、運動の期間・時間・頻度という指標を1つにまとめた“総実施時間”を指標として、運動に取り組むことを提案しております。
今回は、高齢者の方の運動の目安となる“総実施時間”に焦点を絞ってご説明を致します。
総実施時間とは?
私は、専門学校の2年生の前期に初めて“総実施時間”という尺度があることを学習しました。
総実施時間は、高齢者を対象とした運動の介入に関する151つの論文から総実施時間を求め、8〜12時間、13〜24時間、25〜48時間、49〜72時間、73時間以上の5つに分類し、筋力、骨格筋量、身体機能といったoutcomeへの影響を検証したものです。
アウトカム(outcome)とは、医療機関で検査や治療を行い、その結果を評価して得られる状態の変化を指します。
その結果、運動の総実施時間が25時間/year以上となるにように運動することで、outcomeが改善する傾向にあることが判明しました。
25時間/year未満でも効果がないわけではありませんが、より安定した効果を求めるためには、25時間/year以上の運動の実施が必要だと言えます。
以下の条件に設定することで25時間/yearの総実施時間を確保することができます。
・期間:半年以上
・時間:60分/回
・頻度:1回/week
医療機関では、医療保険によるリハビリテーションが受けられる期間が制限されています。
・脳血管疾患等リハビリテーション:180日
・運動器リハビリテーション:150日
・心大血管リハビリレーション:150日
・廃用症候群リハビリテーション:120日
・呼吸器リハビリテーション:90日
そのため、理学療法士(Physical Therapist:PT)は、自宅で継続して自主的に自立してトレーニングに取り組むような行動変容的な介入も重要となります。
おわりに
運動の期間・時間・頻度・負荷量の組み合わせは無限にあり、現病歴、既往歴、職業歴、生活歴などの個人因子を考慮した場合、万人ウケする最適解を導くことは不可能です。
そこで、運動の期間・時間・頻度という指標を1つにまとめた“総実施時間”を指標とすることを提案させていただきました。
筋力、骨格筋量、身体機能などのoutcomeに対しては、運動の総実施時間を25時間/year以上確保することが重要だと考えられています。
医療保険でのリハビリテーションには制限を受けるため、高齢者サロンなどへ参加して、自主的に健康を維持する必要があります。
もし、企画の立案にお困りのことがありましたら、講師としての実績が多数ある当社にご相談ください。
BooSTは合同会社MYSと連携して訪問リハビリテーションを提供しています。
五島市にお住まいの方はこちらのホームページもご覧ください。