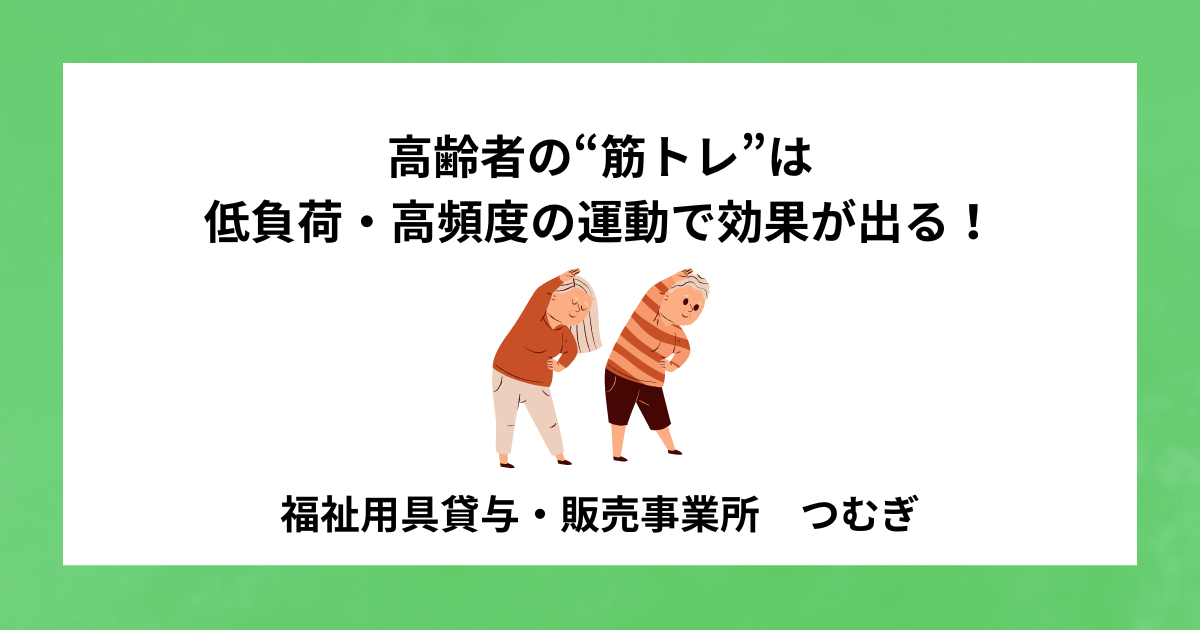
こんにちは。株式会社BooSTの畠山です。
今回は「高齢者の“筋トレ”は低負荷・高頻度の運動で効果が出る!」について解説します。
参考文献
今回は「イチからわかる!サルコペニア Q&A」を参考にさせていただきました。
筆者は筑波大学 山田 実氏です。
リンクを記載しますので、詳細を知りたい方はご参照ください。
https://www2.human.tsukuba.ac.jp/faculty_j/yamada-minoru
はじめに
一般的に筋力や骨格筋量のUPを目指すためには、最大挙上重量(1RM:Reperition maximum)の70〜80%の負荷量で実施することが推奨されています。
しかし、1RMの70〜80%は高負荷に該当します。

最近の研究では、高齢者が対象である場合に限り、1RMの70〜80%の負荷量でなくても筋力と骨格筋量のUPが可能だということが判明し、負荷量の設定方法が再検討されています。
低負荷でも効果が得られるのか疑問に感じている方は多いと思います。
実際、私が理学療法士として講師を務める際には、必ず運動の負荷量に関する質問を受けます。

しかし、負荷量の違いによって筋力や骨格筋量の改善に明確な差が報告された研究はありません。
では、筋力や骨格筋量を改善するためには何が重要だと思いますか?
本日は、高齢者の筋力や骨格筋量の負荷量についてお話しをしたいと思います。
高齢者の筋力や骨格筋量のUPに必要な仕事量とは?
高齢者の骨格筋の機能を改善・向上させるには“仕事量”が重要だと報告されています。
仕事量は以下の式で算出することが可能です。
仕事量 = 負荷量 × 総反復回数
総反復回数 = 回数 × 数
高齢者の場合、高負荷・低頻度での筋力増強訓練は重要ではありません。
最近の研究では、低負荷・高頻度での運動で一定の効果が期待できるという結論が出ています。

低負荷・高頻度でのトレーニングでは、resistance exerciseと比較して有酸素運動の効果の方が強くなることに懸念があるかもしれません。
○resistance exercise

筋肉に負荷をかけて、繰り返し行う運動を指します。
筋蛋白質の同化が促進されるので、骨格筋量の増加には非常に有効です。
○有酸素運動

長時間継続して行う運動を指します。
有酸素運動は蛋白質の同化を促進する作用は認められていません。
しかし、蛋白質の異化を防止する機序は証明されているため、サルコペニアの治療に有効である可能性があります。
高齢者の場合、運動の種類に関わらずtypeⅠ線維とtypeⅡ線維どちらも増加します。
○typeⅠ線維
typeⅠ線維は“赤筋”を指しており、“筋持久力”に影響を及ぼしています。
そのため、駅伝やマラソンを専門としているアスリートで赤筋の割合が高いことが報告されています。
typeⅠ線維では加齢による退行性変化の影響を受けにくいことが特徴です。
○typeⅡ線維
typeⅡ線維は“白筋”を指しており、“筋瞬発力” に影響を及ぼしています。
そのため、100m走などを専門にしているアスリートで白筋の割合が高いことが報告されています。
typeⅡ線維では加齢による退行性変化の影響を受けやすいことが特徴です。
表に違いをまとめました。

高齢者の場合、typeⅠ線維が優位となるため、姿勢を保持することが困難となり、円背(猫背)の原因となります。

併せて読みたい記事
↓猫背の原因は〇〇○筋が原因!?〜理学療法士が”歩行”にこだわる理由〜↓
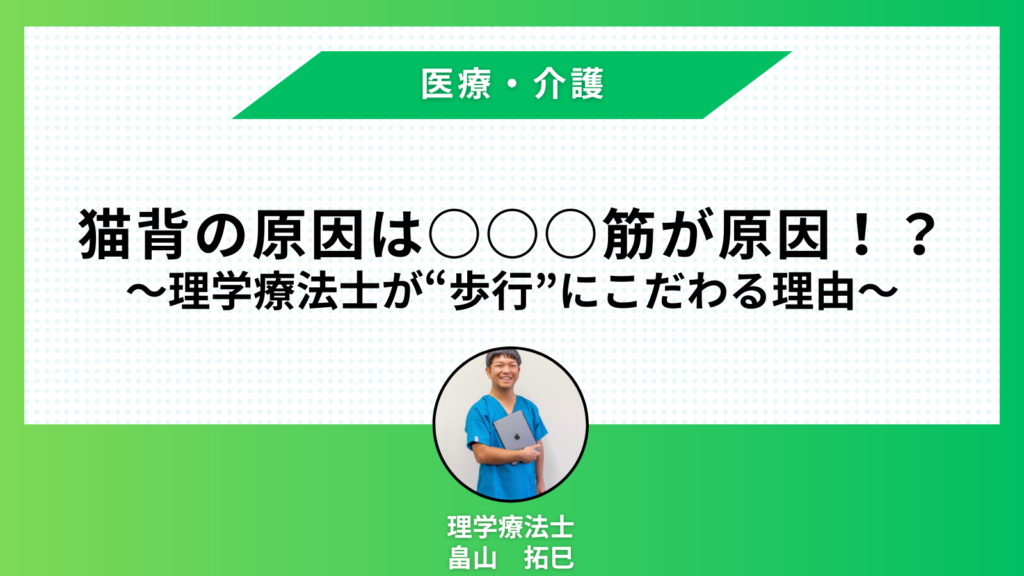
おわりに
入院すると、毎日のように理学療法士が治療に携わります。
しかし、運動習慣がない方にとって、運動は非常にストレスになり、逃げるように退院される方も多いことも事実です。
しかし、これは医療費の無駄遣いです。
急性期や回復期のリハビリテーションに携わっている理学療法士は、退院後の在宅生活も視野に入れた介入を行う必要があります。

まずは対象となる高齢者が自宅でも実施しやすい運動を考案することが重要です。
一般的に、筋力や骨格筋量のUPを目指す場合には、高負荷での運動が推奨されます。
しかし、高齢者が対象である場合には、低負荷・高頻度での運動で一定の効果が期待できます。
つまり、仕事量を意識した運動を提案することが重要です。
BooSTは合同会社MYSと連携して訪問リハビリテーションを提供しています。
五島市にお住まいの方はこちらのホームページもご覧ください。